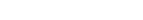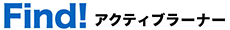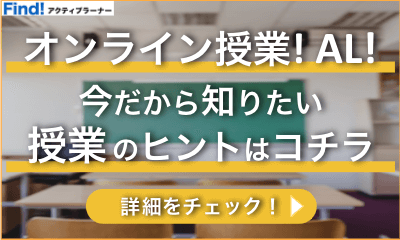探究学習とは
~新科目「探究」の基礎、基本をご紹介!~
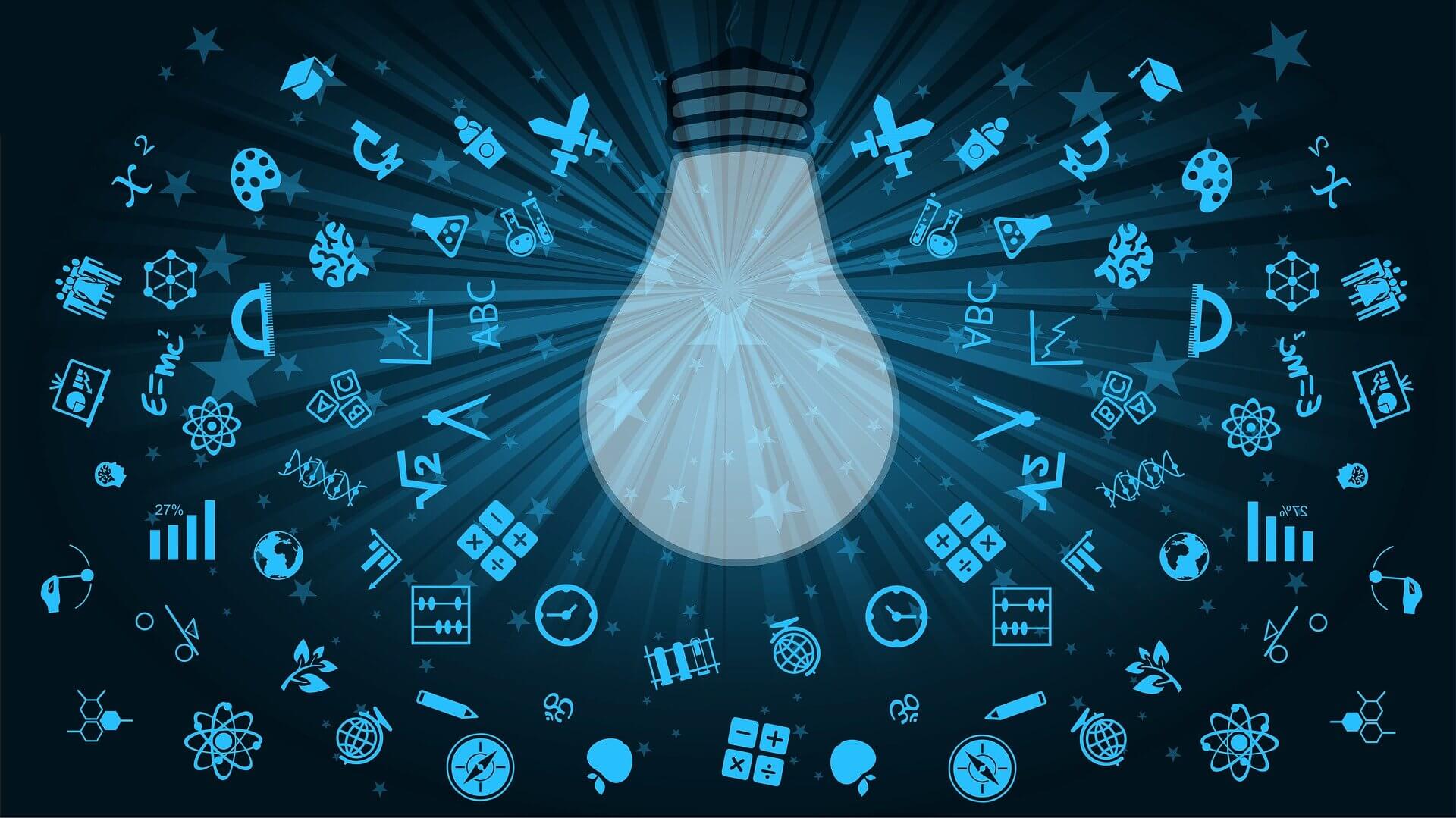
《子どもたちが夢中になって取り組む授業》のヒント公開中!
Find!アクティブラーナーは、全国で主体的・対話的で深い学びを実践する先生方の授業をWebで見学・研究できるサービスです! オンライン授業含め、その実践例や教授法・ノウハウなどを動画で配信しています!
withコロナ時代、子どもたちに学びを届けるためのヒントをぜひお受け取り下さい!
詳しくは ⇒コチラ
本記事は、現代社会に求められる「探究学習」について理解するための内容が掲載されています。ここでは、探究学習の概要と探究学習が求められる社会的な背景について知り、さらに実践例や具体的な計画方法についても知ることができます。
【目次】
1,探究学習とは ~「探究」と「探求」の違い~
「探究」とは、物事の本来の姿やあり方を探り、その物事を明らかにする、あるいはみきわめることを意味する言葉です。「探求」は、物事を得ようと探し求めることを意味する言葉です。「求める」という漢字が使われていることから分かるように、「探求」は物事を追い求めて行動していきます。
それに対して、「究める」という漢字が使われている「探究」は深く掘り下げて学び、物事をみきわめようとします。
同じ「たんきゅう」という発音の言葉ですが、両者にはこのような違いがあります。
「究める」という漢字を用いた「探究学習」は問題解決型の学習であり、生徒自らが課題の解決に向けて動いていく連続した学習活動です。
生徒は自分で課題を設定し、情報の収集、整理、分析をおこない、時には周囲と協働しながら課題解決に向けて学習を進めていきます。
この一連の学習活動によって、思考力や判断力といったスキルが育成され、表現する力も養うことができるとされています。
2,探究学習が求められる背景と、新学習指導要領での扱い

では、なぜこのような探究学習が求められているのでしょうか。
それを解くためのキーワードは、「新しい時代」です。
現代は、将来の社会のあり方が予測しにくい時代です。AIの登場と進化により社会の情報化は加速傾向にあり、現代の子どもが仕事に就く年齢を迎える頃には、従来の多くの仕事がAIに置き換えられ、人類は今は存在していないまったく新しい職業に就くと予想している学者もいます。
また、今も進行中である少子高齢化は、2030年を迎える頃さらに進行し、生産年齢人口自体も大きく低下すると考えられています。
このような予測に伴い、日本のグローバル化の遅れやIT教育の遅れを挽回しようという動きがみられるようになりました。10〜20年先の国際社会で生きていく力を身につける教育が、今必要とされているのです。探究学習が求められる背景には、このような状況があります。
このような教育の変革に対して、文部科学省による新学習指導要領には、「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」という文言で探究的な学習の重要性がふれられています。
校種ごとの新学習指導要領における探究学習の位置づけについて、具体的に見ていきましょう。
小学校における位置づけ
小学校の新学習指導要領において、探究学習は「総合的な学習の時間」に位置づけられています。児童の探究学習においては、身の回りで起こる物事から課題を見つけることがよいとされています。課題の発見とその解決に至るまでの情報収集、整理分析は、なるべく先生の手を借りることなく児童が遂行することが推奨されているので、身近な問題から探すのが現実的でしょう。
中学校における位置づけ
中学校の新学習指導要領における探究学習も、「総合的な学習の時間」と位置づけられています。生徒が自ら課題を見つけて設定し、横断的かつ総合的な学習をおこないながら、課題解決のための能力を育成する目的でおこなわれます。
学習がよりよくおこなわれるためには、課題の設定、情報の収集、整理と分析、まとめ・表現というプロセスが明示される必要があります。教科の枠を超えて横断的に情報を集めて分析し、意見交換をしながら解決を目指します。
高等学校における位置づけ
高校の新学習指導要領における探究学習は、「総合的な探究の時間」になります。生徒が主体的に課題を設定して、情報の収集、整理と分析をおこなって課題解決のための能力を養います。
高校における「総合的な探究の時間」は、その内容が特定の科目や教科にとどまることなく総合的で横断的でなければならないという点が重要です。時には大学や研究機関、企業といった外部の協力も視野に入れて、課題解決に向けた発展的な学習をおこないます。
なお、学習の具体的な進め方については、第4章で順を追って解説します。

・アクティブ・ラーニングについて、実はよく知らない…
・本では勉強したけど、実際の授業イメージが湧かない…
・一方通行型の授業に限界を感じているがどうすれば…
・生徒の理解をより深め、将来につながる授業をしたい!
アクティブ・ラーニングの最新情報、明日の授業で使えるスキル・ノウハウを“授業動画”を観ながらインプット!詳しくはコチラ▽▼
3,探究学習の現状
第3章では、探究学習のより現実的な側面に焦点をあてます。つまり、探究学習が実際の教育現場でどれくらい実施されているのか、また取組みにおいてどのような課題があるのかという点について解説します。
まず、高校における2019年度の探究学習科目実施状況は、実施する科目によって異なりますが概ね8.1%〜13.5%でした。
また、約15%〜20%の学校は数年以内に探究学習を実施する予定であると回答していますが、70%前後の学校は今のところ探究学習を実施する予定がないか分からないと回答しています。※
探究学習が浸透しない理由としては、授業時間が足りない、実施についての資料や横断的な連携が間に合わないなど、色々な原因が想定されます。高校の探究学習の課題、不安については「生徒への評価が難しい」、「指導内容に不安が残る」、「学習場所が広範囲になり過ぎる」、「十分な学習計画が作成できない」、「学習計画通りに授業が進まない」と回答する教員が多くいました。
また、「保護者からの理解が得られない」、「支援してくれる大学や企業が見つからない」、「生徒の授業に対するモチベーションが低い」といった点を問題視する声もあります。※
授業として実施する以上、何らかのかたちで評価が必要です。ただし、探究学習における学びのあり方は通常の科目より横断的であり、絶対的な正解がない中で解決策を探し当てていく場面も少なくありません。このような課題は評価の仕方が難しく、一律的な評価軸を定めにくいというのが授業実施におけるハードルになっています。探究のような学習の場合、教員は課題解決の結果だけを評価するのではありません。それぞれの児童・生徒がおこなう情報収集の手法や、まとめ・表現にいたるまでの道筋をみて、評価を下すことが求められます。
探究学習の実施について課題は少なくありませんが、自発的な学びの姿勢や、グローバルな視点をもって物事に向かう力を育成するために有益な学習であり、探究学習は大学の総合型選抜(旧AO入試)、学校推薦型選抜(旧推薦入試)などで有利になる可能性もあります。
先に、探究学習の浸透しない理由のひとつとして「保護者からの理解が得られない」というアンケート回答がありましたが、数年後にはむしろ保護者のニーズが高まってくる可能性も想定されます。特に高校や中高一貫校においては、大学進学に向けた取り組みとして探究学習の可能性や必要性について着実に準備を進めていく必要があるでしょう。
※実施状況、課題に関するアンケート結果は、いずれも一般社団法人英語4技能・探究学習推進協会調べ。
4,探究学習の実践について

探究学習の実践においては、教育者がまず「課題設定」「情報収集」「整理・分析」「まとめ・表現」といった活動内容について理解しなくてはなりません。これらの過程を明示することで、児童・生徒は探究学習を正しく進めることができるようになります。児童・生徒がそれぞれの過程で何をすべきか、それを具体的に思い描けるように進めていきましょう。
(1)課題設定
課題設定とは、探究学習で解決すべき課題を児童・生徒自身が見つけるプロセスのことです。小学校・中学校ではいきなり社会的で大きな問題を取り上げるのではなく、学校生活や自分の身の回りのことなどから、困っていること、解決したらよりよい生活になると思われることを探すよう誘導していくと進めやすくなります。
課題設定の際に留意するべきポイントとして、児童・生徒が自発的に課題を見つけられるように教員はサポートに徹する、という点が挙げられます。一方的に課題を押しつけたり、一律的な回答が得られるような問題提起の仕方は、探究学習としてふさわしくありません。
また、学習場所が広範囲に渡ったり、予算不足で学習が止まってしまうという事態も避けたいところです。これらの事態が起こらないよう、事前の学習計画は無理のないよう実現可能な範囲をよく検討しておく必要があります。
(2)情報収集
情報収集とは、課題にまつわる情報や、解決に役立つと思われる情報を収集するプロセスをさします。情報収集は教科の枠にとどまらずおこなわれるべきで、特に高校の探究学習においては学校外(大学、研究機関、企業など)との連携も積極的に考えていくとよいでしょう。
スムーズな情報収集のためには学校外部の連携が事前に必要なケースもありますが、思ったように支援提携先が見つからないという悩みもあるようです。
その場合は、教育委員会や自治体に問い合わせるか、文部科学省の「総合的な学習の時間応援団」のページから支援団体を探してみましょう。
・文部科学省「総合的な学習の時間応援団」
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/sougou/syokatsu.htm
(3)整理・分析
整理・分析とは、前のプロセスで収集した情報を課題解決に役立つかたちにしていく作業です。情報は集めただけでは解決の助けになりません。情報の取捨選択をおこない、解決に役立つ情報とそうでない情報を振り分ける、複数の情報を組み合わせてより有益な情報としてまとめる(グラフ化、図形化など)といった作業をおこないます。
すでに収集したAという情報を役立てるためにはBという情報が必要である、となった場合には一時的に前のプロセスに戻り、もう一度情報収集を実施することも求められるかもしれません。集めた情報を課題解決に対して使えるデータにするというのが、この過程ですべきことです。
整理・分析の段階では、作業が単調になっていないか、児童・生徒のモチベーションが低下していないかをチェックすることが重要なポイントになります。分析の手法によっては、まとめにたどり着く前に飽きてしまい、解決まで至れないケースも考えられます。課題と向き合う好奇心が持続するような整理・分析のあり方は、授業計画の段階で検討しておく必要があります。
(4)まとめ・表現
まとめ・表現とは、児童・生徒が自身で収集、分析した結果を客観的にあらわす段階をいいます。物事の探究は、情報を収集したり分析したりして「何となく分かった気になった」だけでは達成されません。それを第三者に分かりやすい客観的な言葉で表現することが重要です。
情報収集と整理・分析がインプット作業だとすれば、まとめ・表現はアウトプットの作業と位置づけることができます。
まとめ・表現の段階における注意すべきポイントは、見つけた課題に対して一応の「解決」が示されるようにすることです。課題に対して調べるのみで学習が終わってしまったり、意見交換が不十分だと、物事を究める=探究にはなりません。時間配分が足りなくなって無理やりまとめるような授業にならないよう、計画の段階でまとめ・表現に充当する時間を確保しておく必要があります。
5,探究学習の実践例
具体的な進め方について理解したところで、実践例についても見ていきましょう。
事例1 山形市立第三小学校
山形市立第三小学校では、算数の分数について図式化し、自分で説明文を考えてクラスで意見を交換する取り組みが探究学習としておこなわれました。教科書で公式を学ぶだけでなく、「なぜそうなるのか」を主体的に考えて協働的かつ創造的に学ぶ取組みです。
参考URL
https://www.pref.yamagata.jp/documents/5026/7jyugyoukaizenpoint.pdf
https://www.dai3-e.ymgt.ed.jp/R2HP/R2kenkyugaiyou.pdf
事例2 聖心学園中等教育学校
聖心学園中等教育学校の4年生(高校1年)は、「持続可能な社会」を実現させるためのアイデアを探る探究学習をおこないました。この実践例では、スライドやワークシート、映像教材を使い、事例紹介から課題解決分析をおこなう個人ワークまでを50分授業の中で完結しています。SDGsの考え方と日本企業の取り組み、その取り組みの分析と目標を達成するための課題解決方法について探究し、生徒同士がそれらを共有して意見交換もおこなっています。
参考URL
https://www.career-program.ne.jp/ucc/casestudy/pdf/case2.pdf
事例3 茨城県立並木中等教育学校
並木中等教育学校が行う理数探究では、4、5年次(高校1~2年)の2年間をかけて、1人1テーマで探究活動をおこなっていきます。特に4年次は、「自分の問いを見つけること」を目的に、テーマ設定に1年間まるまる使い、探究のためだけでなく将来の進路選択にも活きるテーマを探します。また、5年次からは、探究をただの「調べ学習」にしないよう、「オリジナルデータを必ず取ること」「データを数値化すること」を課します。インターネット上だけでは答えの出せない問いに、自分ならではの答えを出すことで、大人になってからも必要とされる「発想力」や「行動力」といった能力の育成も狙いとしています。
6,探究学習の意義、可能性
探究学習は、児童・生徒が身の回りや社会を見渡して自主的に課題を発見し、その課題を解決すべく教科をこえて横断的かつ発展的に学ぶ学習です。教科にとらわれずに課題解決を目指すという意味では、より現実に即した学びの体験ということもできるでしょう。
予測し難く、これまでの一律的な学問が必ずしも役に立つとはいいきれない現代社会において、子どもの生きる力や可能性を広げるために欠かせない学習活動ではないでしょうか。
\SNSでの拡散大歓迎/

・アクティブ・ラーニングについて、実はよく知らない…
・本では勉強したけど、実際の授業イメージが湧かない…
・一方通行型の授業に限界を感じているがどうすれば…
・生徒の理解をより深め、将来につながる授業をしたい!
アクティブ・ラーニングの最新情報、明日の授業で使えるスキル・ノウハウを“授業動画”を観ながらインプット!詳しくはコチラ▽▼