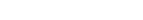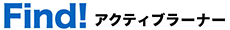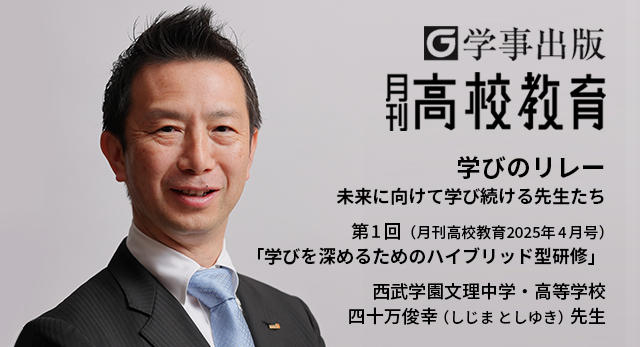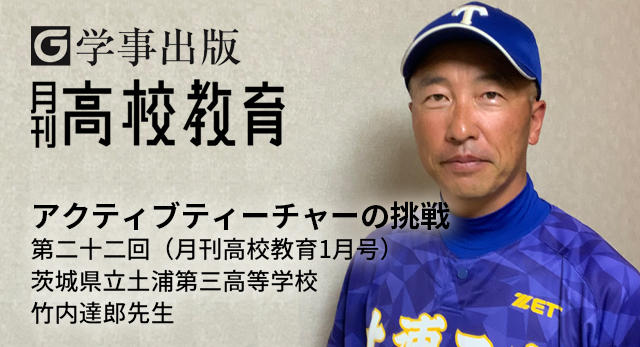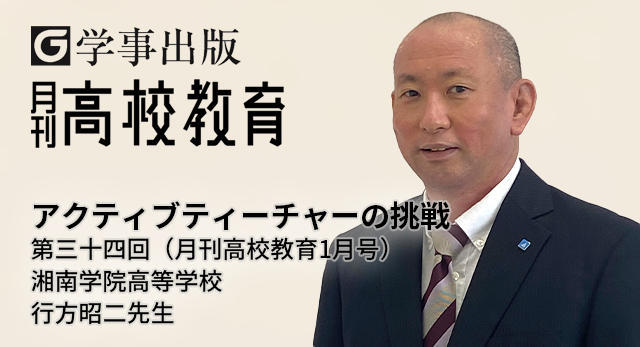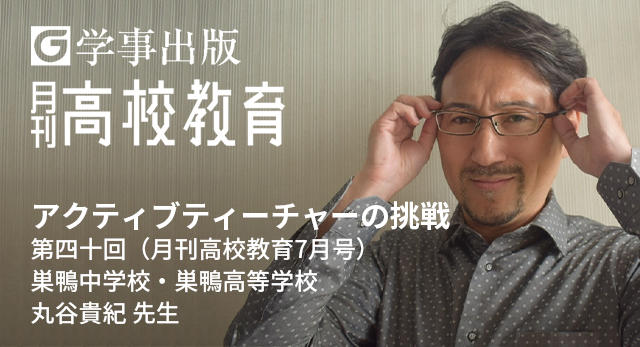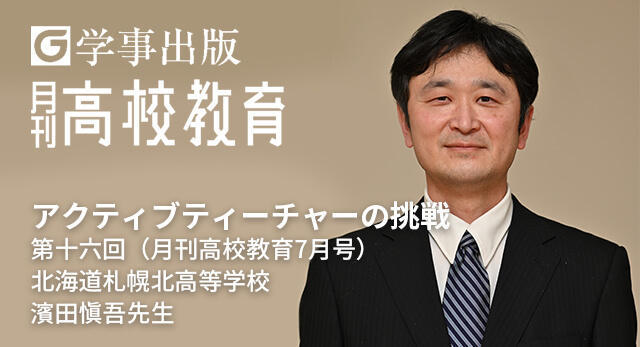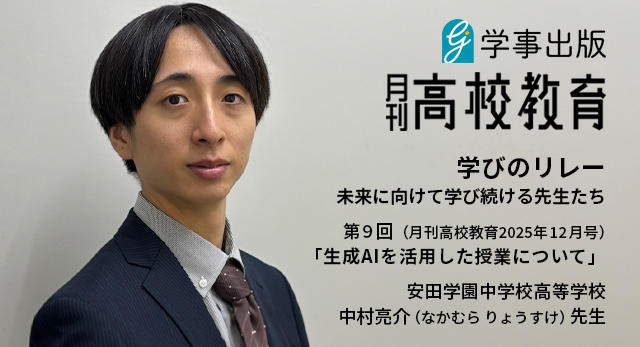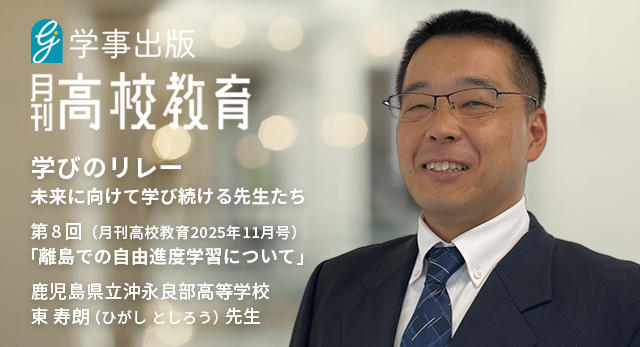学びのリレー 未来に向けて学び続ける先生たち 第5回(月刊高校教育2025年8月号)
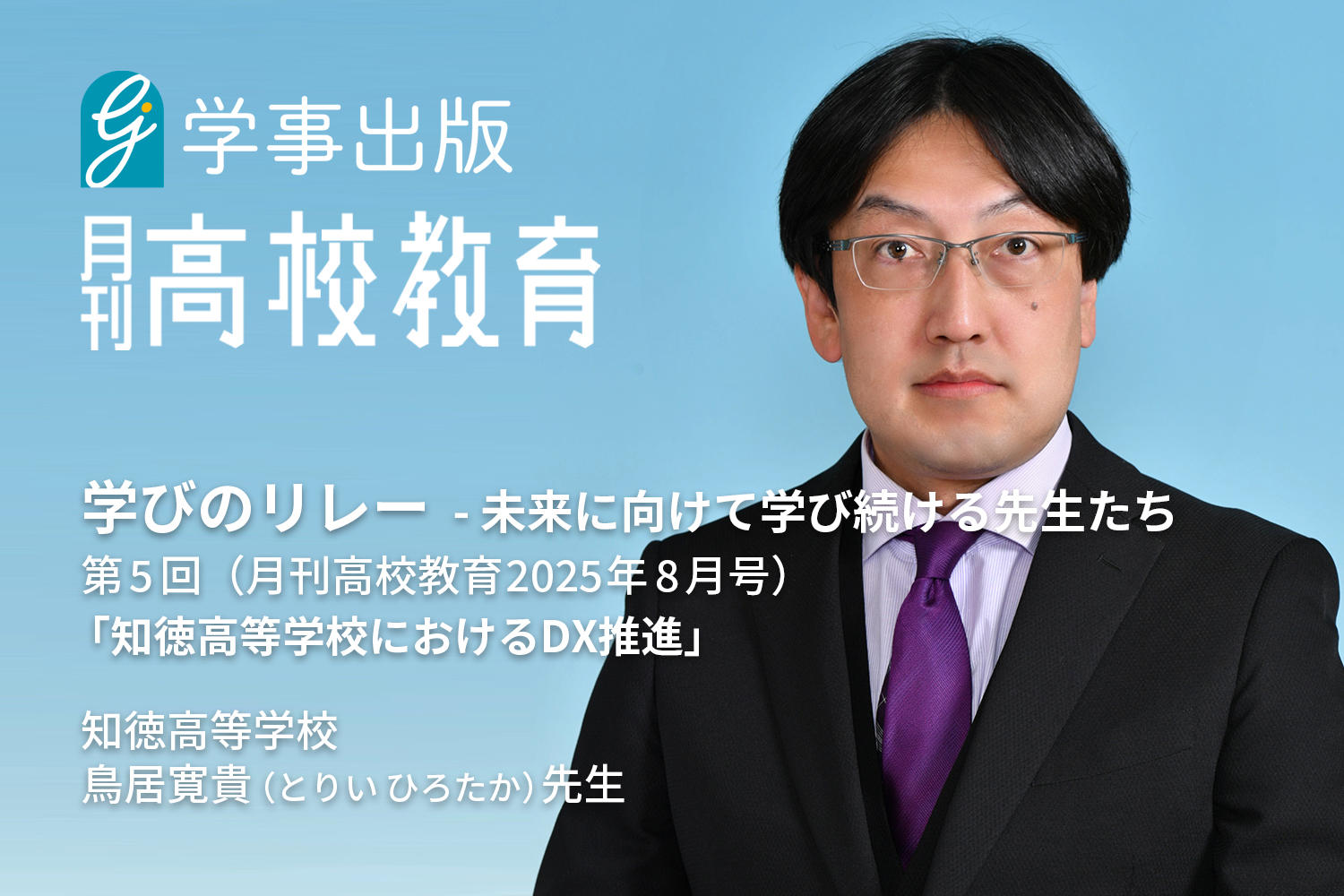
学事出版『月刊高校教育』にてFind!アクティブラーナーの連載がスタート!
こちらでは冊子の記事をWEB版として公開しております。
学びのリレー 未来に向けて学び続ける先生たち 第5回(月刊高校教育2025年8月号)
知徳高等学校
鳥居寛貴(とりい ひろたか)先生
「知徳高等学校におけるDX推進」
≪知徳高等学校について≫
本校は、静岡県駿東郡長泉町に所在する私立学校です。昭和9年に三島家政女学校と三島実践女学校の両校を統合して三島実科高等女学校として創立しました。昭和30年に三島高等学校と改称し男女共学となり、昭和34年に現在の場所に移転しました。平成14年に現在の校舎ができ、平成26年に知徳高等学校に校名を変更、令和5年に創立90周年を迎えました。令和6年には、知徳グローバルフューチャープログラム(海外進学指定校制度)を開始。また、高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)に採択され、令和7年度も継続採択校となりました。
知徳グローバルフューチャープログラムとは、海外へ⾶び出す気持ちを育成し、世界がぐんと⾝近になるグローバルプログラムです。海外⽣活や留学の体験事例紹介から海外⼤学・専⾨学校指定校推薦制度、ワーキングホリデイ⽀援など、様々なアプローチから未来の可能性を広げ、世界を経験できるステップをサポートしています。また、本校では、ソーシャルスキルトレーニング講座、できたことノートなどのSEL教育、「選択させ考えさせる」指導なども行っています。
本校には、4学科9コースがあります。学科は、普通科、情報ビジネス科、福祉科、創造デザイン科の4つです。専門的な学びもできる環境があり、西は静岡方面から東は神奈川県からも電車で通学をしている生徒もいます。目的をもって学ぶ生徒が多く、高校卒業後の進路も多種多様になります。
≪高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)の取り組み≫
○令和6年度の取り組み
情報ビジネス科の令和7年度入学生の教育課程において、ICTソリューションコースでは2年次に「情報Ⅱ」(2単位)、3年次に学校設定科目で「データサイエンス」(2単位)を設置しました。そのために、大妻女子大学データサイエンス学部の先生方にご教授いただき授業内容の検討、データサイエンスを実施している高等学校への視察等を実施しました。また、校内では教職員を対象にした情報リテラシー研修なども実施しました。
情報ビジネス科の取組では、2年次より2年間かけて課題研究の授業を履修します。令和5年度から実施した課題研究の授業では、地域経済分析システム(RESAS)を活用した学習を内閣府地方創生推進室、関東経済産業局の方々と連携して実施しました。本年1月には発表会を実施し、多くの方に生徒の発表を聞いていただきました。また、地域の小学生を対象としたプログラミング教室等も開催しています。
施設面では、探究学習及び遠隔授業の拠点とすべく関係設備を整備し、対話的・協働的な学びの充実に向け、テーブル付き可動式のミーティングチェアなども整備しました。
○令和7年度(継続2年目)の取り組みの予定
令和6年度に続き、8年度から始まる「情報Ⅱ」、9年度の「データサイエンス」開設に向けた教材準備のために大学や企業が主催する教職員向けの研修会等への参加、また他の学校への視察などを行い、教職員のスキルを身につけた能力の育成を図っていきたいと考えています。さらに、AIの活用についても、生徒が正しい使い方ができるような取り組みができればと思います。
施設面においては、探究学習及び遠隔授業で対応できる環境をより充実させるとともに、本校の特色でもあるグローバルフューチャープログラムの1つとして、海外の高校生とオンラインや対面による交流機会などを増やすことができればと考えています。
≪デジタル化による業務負担の軽減≫
各教室にプロジェクターとApple TVを設置したことにより、多くの教員は、ノートPCやタブレット端末等を活用して授業を展開しています。データの共有をしながら各クラスのニーズにあった授業展開が出来るようになりました。教職員の取り組みとして、授業以外にも下記項目等で、デジタル化による業務負担の軽減に取り組んでいます。あわせて、業務負担軽減だけでなく、学校経費の削減にもつながっていると思います。
○ペーパレス化……会議資料や出張申請復命等
○採点業務……自動採点システムを導入し採点業務の軽減とデータ利活用
○保護者との連絡……通知表やテスト個票、欠席連絡、保護者宛の文書等
○生成AIの活用……「FCEプロンプトゲート・アカデミック版」の活用
○校務支援システム……校務支援ツールを使用し、生徒の出欠状況、教職員間の連絡、施設の予約、教職員の動静なども確認ができます。
上記のDX推進によって、日常業務の削減・効率化がすすんでいると思います。出欠について担任、教科担当がすぐに確認ができます。テストデータなども利活用し、生徒が苦手としている部分の対策を考えることもできます。また、本校では朝の打合せと昼の打合せを2回実施していましたが、校務支援ツールを活用し、打合せは朝のみとなり連絡事項等は支援ツールの機能を活用して行っています。私自身はまだまだできていませんが、遅くまで職員室に残る先生も減ったように感じます。
≪私の日々の学び・研鑽について≫
私は、現在情報ビジネス科の学科長、教科主任(商業・情報)、DXの事業を担当しています。そのため、教科やDX等に関係する研修等には積極的に参加するよう心がけています。近年は、オンラインによる研修会が多く開催されていますが、私は、出来るだけ対面での研修会に参加するようにしています。なぜなら、対面だと講師の先生に直接会って質問もすることができるからです。
私立高校では、公立高校の先生方のように異動がほとんどないため、他の学校の先生と交流をもつ機会は少ないのが現状です。そこで、研修会等に参加することで、県内の先生方だけでなく県外の先生方とも交流や情報交換をすることができ、有意義な時間を過ごすことができます。また、1回の研修だけで終わってしまうのではなく、その後も先生方と情報交換をさせていただくように心がけています。
さらに、学校関係者だけでなく行政の関係者や民間の企業の方などとも交流をするようにしています。多くの方と交流することで、出前授業等で講師をお願いし、協力していただける機会もあります。そのことで、生徒にとっても学習の良い機会にもなると思います。
≪教育の未来について≫
現代の社会はVUCA時代とも言われ、スキルセットとマインドセットが大切とされています。スキルセットではITリテラシーや課題解決能力、コミュニケーション能力などが求められます。また、マインドセットではOODAループなどが注目されています。
このようなVUCA時代で求められている力は、学校教育においても必要な内容だと思います。そして、今は次期学習指導要領の内容を中心とした話題が多くあり、学事出版の『月刊高校教育5月号』でも次期学習指導要領、改訂議論がスタートと特集で掲載されています。
教育の未来は、次期学習指導要領の内容を中心に進んでいくと思いますが、DX事業や商業・情報を担当していて思うことは、生成AIをどのように学校教育に導入するかです。これは、生徒のことを考えると未来ではなく、実際には直近の課題になるかもしれません。生徒が時代のニーズに対応できるようにするためにも、日々の取り組みを大切にするとともに、必要な情報発信をしっかり行っていきたいと考えています。
≪読者の方へのメッセージ≫
DXという言葉が日本で広く知られるようになって5年以上が経過しています。DXの導入により教育現場においても大きく変わっています。私自身も日々新しいことを学ぶことが多くあります。自分の持っているスキルだけでは対応できないことも多々あり、本校の教職員をはじめ、多くの先生方のサポートがあるからこそできることもあります。
デジタル化により教職員の業務軽減は多くのことで実感できますが、対面による人とのコミュニケーションの大切さも改めて実感する日々です。これからも時代のニーズに対応した取り組みを行っていくとともに、私自身が学んだことを一つでも多く還元していきたいと思います。
高校生活の3年間は、生徒一人ひとりにとって大切な時期ですので、これからの未来で活躍する生徒を一人でも多く育て、3年間そこで学んで良かったと思える環境を作っていきましょう。