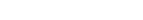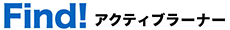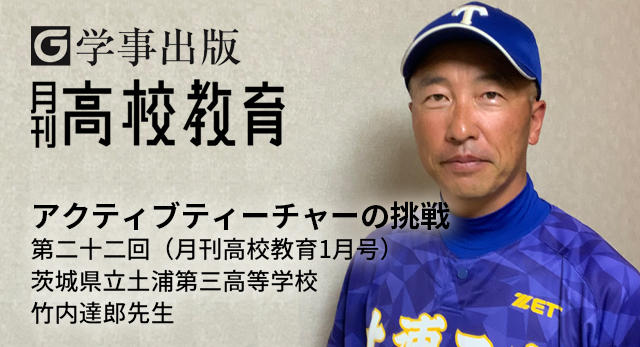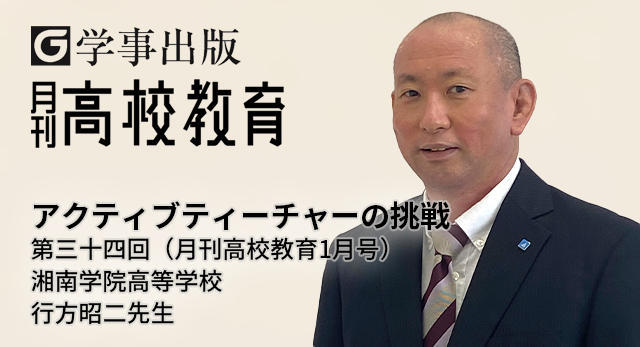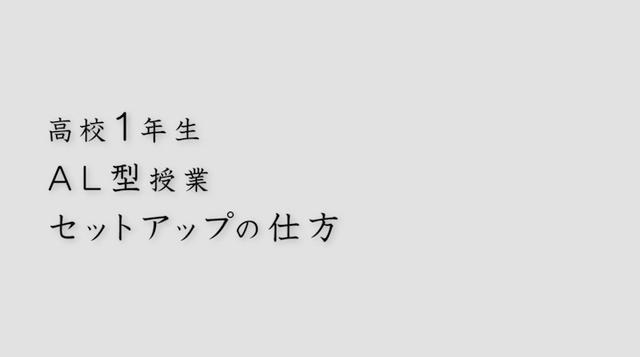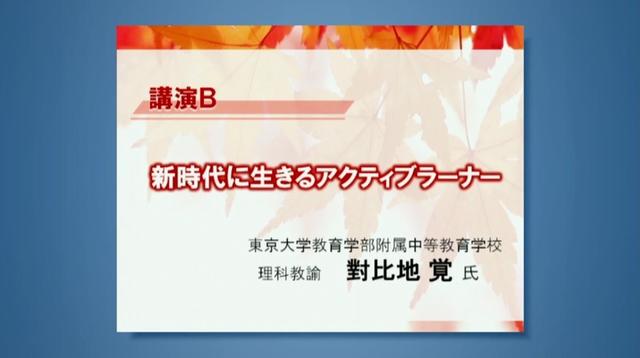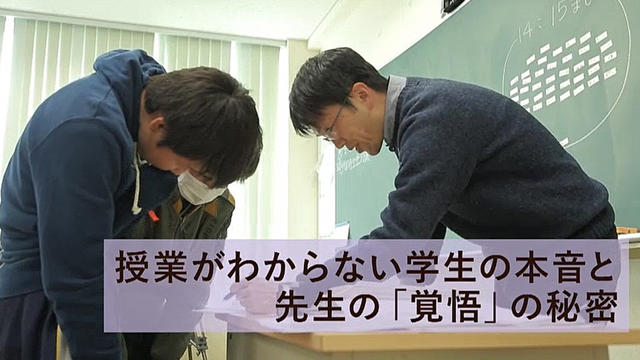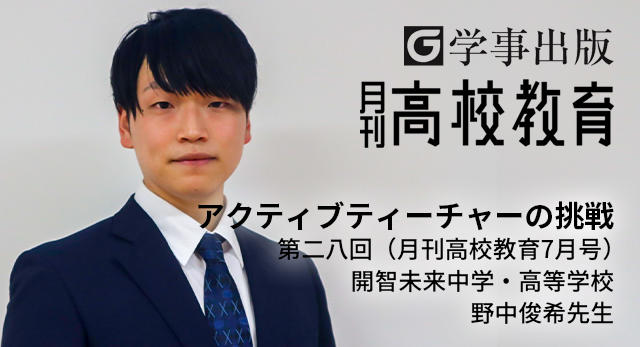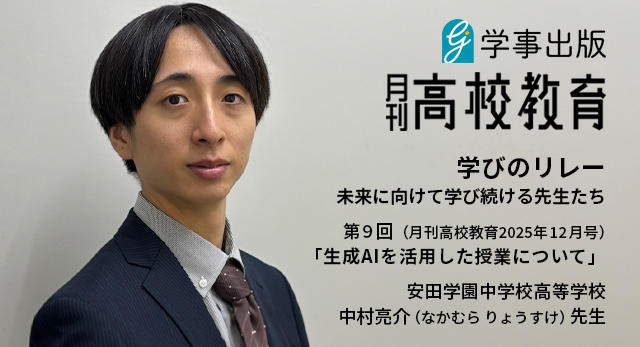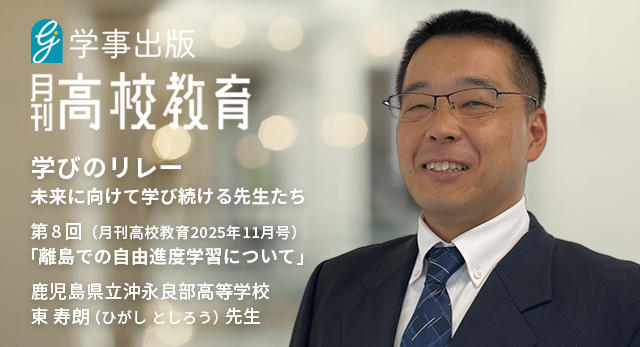学びのリレー 未来に向けて学び続ける先生たち 第8回(月刊高校教育2025年11月号)

学事出版『月刊高校教育』にてFind!アクティブラーナーの連載がスタート!
こちらでは冊子の記事をWEB版として公開しております。
学びのリレー 未来に向けて学び続ける先生たち 第8回(月刊高校教育2025年11月号)
鹿児島県立沖永良部高等学校
東 寿朗(ひがし としろう)先生
「離島での自由進度学習について」
≪鹿児島県立沖永良部高等学校について≫
本校は、鹿児島県の沖永良部島に所在する県立高等学校です。1949(昭和24)年に、沖永良部学校組合立として設立され、1953(昭和28)年の奄美群島の日本復帰と同時に県立高校として認可されました。沖永良部島唯一の高等学校で、普通科2クラス、商業科1クラスの計3クラス、生徒数は約220人になります。
沖永良部島は、人口約12000人、鹿児島県と沖縄県の間に位置する隆起サンゴ礁の島で、周囲約56kmの平坦な地形が特徴です。鹿児島空港からプロペラ機に乗り、85分で沖永良部空港に到着します。温暖な気候で「花と鍾乳洞の島」として知られ、特にエラブユリやキクなどの花卉栽培が盛んです。また、地下には200~300もの鍾乳洞があり、ケイビング(洞窟探検)を楽しむこともできます。島の周囲は透明度の高い海で、シュノーケリングやダイビングが楽しめます。歴史的には、西郷隆盛ゆかりの地で、西郷が流刑中に「敬天愛人」の思想を育んだ場所としても知られています。
本校では、ほとんどの生徒がバイク通学をしています。進学してくる生徒のほとんどが島内で育ってきているため、先輩・後輩というより、地域の仲間という関係で、上級生を「○○兄ちゃん、○○姉ちゃん」と呼ぶ生徒も多く、また、兄弟姉妹、親戚もかなり多く在籍しています。校内には大島特別支援学校高等部の沖永良部教室もあり、一部の授業や学校行事、部活動をともに行っています。沖永良部島にも沖縄同様に伝統芸能であるエイサーもあり、本校のエイサー部は、9年連続で全国高等学校総合文化祭(総文祭)に出場しています。
本校の生徒は、穏やかで素直な性格の心優しい生徒ばかりです。一島一校であるため、少子化の影響で、定員割れが続いているため受験すればほぼ合格という状況もあり、生徒間の学力差はかなり大きく、家庭での学習習慣が身に付いていない生徒がほとんどです。また、高校を選んで受験してきたという意識はそこまで高くなく、小中学校の延長で入学してきたような雰囲気であるため、進路希望が多種多様です。PC・タブレットの普及により、インターネット上の情報はある程度入手できるわけですが、看護体験やオープンキャンパスなど、自分の目で確かめる機会は少ないようです。
≪私のキャリアについて≫
私が数学科教員を目指したきっかけをお話しします。もともと算数・数学が好きだったことと、中学校時代にお世話になった数学の教科担当の先生のようになりたいと思ったことがきっかけです。大学では数理情報科に入学し、統計学のゼミに入り大学院まで進学して統計学を学んでいました。
採用試験になかなか合格することができず、鹿児島県立鹿児島南高校で4年間、数学の期限付き講師として勤務しました。勤務して4年目で鹿児島県の採用試験に合格し、その後鹿児島県の数学の教員として、初任の4年間を国分高校、その後7年間を志布志高校にて勤務し、現在沖永良部高校で4年目を迎えています。
≪離島での教育について≫
鹿児島県の高校の勤務地は、AからFまでの6地区に分かれており、F地区である離島を含め、最低3地区で勤めることになっています。したがって、鹿児島県の全教職員は、定年までの間に離島での勤務を1度は経験します。離島での勤務年数は、一般に4年~5年であり、学校によって勤務年数が決まっています。
鹿児島県の離島には、奄美大島の奄美看護福祉専門学校以外、大学・短大・専門学校等の上級学校がないため、高校から先に進学しようと思えば、ほとんどの生徒が親元を離れて生活することになります。離島によっては高校もない島があるため、高校生から親元を離れる生徒もいます。そのことは、一般的に「島立ち」と呼ばれ、就職するにしても進学するにしても、高校卒業後はほとんどの生徒が「島立ち」しなければなりません。
本校は、全国総文祭に、エイサー部が郷土芸能専門部門に9年連続、校内の弁論大会で優勝した生徒が弁論部門に3年連続で出場しています。また、2024年7月に中島博司先生(元茨城県立並木中等教育学校校長)を講師にお招きして、文章メソッドであるR80についての講演会を開催することができたため、各行事や授業の振り返りとしてR80を活用しています。そのほか、台湾の高校との交流や、島外の生徒に入学してもらうための「地域みらい留学」の取り組みにも着手しているところです。
また、鹿児島県が本年度から、Zoomを使った遠隔授業に取り組んでおり、本校も参加しています。現在、情報を計4単位、数学を計5単位、遠隔授業で行なっています。初めての取り組みのため試行錯誤の連続ですが、生徒への細やかな配慮、職員の負担軽減にも繋がっているので導入してよかったという感想が多いようです。
離島の高校では、外部からの情報が入りにくい環境であることから、教員の指導に対してとても素直に応じる生徒が多く、授業をはじめとした指導上の工夫などがそのまま生徒の成長に繋がることが多いため、生徒と二人三脚で取り組んでいる実感を得やすく、やりがいは大きいと思います。また、塾やスポーツのクラブチームに通っていないため、学力や身体能力に関して大きな可能性を秘めている生徒も在学しています。そういった生徒たちが、教員の予想を越えて成長していく楽しみもあります。
一方、前述した通り1島1校の学校であるため、少子化の影響は大きく、定員割れが続いています。そのため、生徒の学力差が大きく、授業を行う上で焦点をどの層に当てて授業を展開していくかが大きな課題になっています。職員の数も少ないため、習熟度に合わせたクラス編成も十分には行えていません。
また、生徒に島外で様々な体験をさせたいと考えたときに旅費が高額になるため、実施回数が限られてしまうことも課題です。大会などの参加にしても、講師の先生を招聘するにしても、旅費がかなり高額になってしまいます。併せて、海風の影響による建物の劣化への対応、高温多湿な気候に対応するための空調費の確保など、様々な面で南の離島特有の費用が必要となるため、金銭面での課題は大きいと感じています。
≪自由進度学習について≫
自由進度学習に取り組むきっかけは、本校の生徒の学力差が大きいことでした。1クラスに様々な学力の生徒が在籍している状態で、どのような授業を展開をしていくかを日々悩んでいました。苦手な生徒に合わせた丁寧な授業展開では、力のある生徒を伸ばすことができず、伸び悩んでしまうことがあり、その逆もありました。そのときに、教育雑誌で、自由進度学習を行なっている先生の記事を見て、生徒1人1人に合わせた授業を行うヒントになるかもしれないと思い取り組んでみました。生徒1人1人の理解度に応じた授業を行うとともに、生徒自身に適した学習の方法を身につけてほしいという目的で、チャレンジしています。
【私が実施している数学の自由進度学習の方法】
① 2週間ごとに単元テストの実施を予告したおおよその進度表を配付して、単元テストまでにその範囲の教科書のページが終了することを目標として、それぞれ取り組ませています。進度は一番数学が苦手な生徒に合わせています。
② 教科書に合わせた板書風のまとめデータは、事前に生徒に配付して、わからないときはそのデータを見ること、周囲の友人に尋ねること、直接私に尋ねること、YouTubeなどのネットを活用することなど、学びに繋がる行動は全て許可しています。また、早く進められる生徒の課題も、別に用意しています。
③ 授業中は生徒1人1人の状況を見て周り、アドバイスをしています。進度が早い生徒に次にするべきことを提案したり、できなくて悩んでいる生徒の質問に答えたり、苦手な生徒のできない原因を一緒に考えて必要な学び直しを提案したりと、生徒1人1人の理解度や進路希望に合わせた声かけができるように心がけています。
④ 私自身が全く講義をしないわけではなく、進度表に合わせて、授業の最初に5~10分くらい説明をすることもあります。なお、特別教室を使い25名くらいで実施しているため、座席については、生徒の自由に任せています。
【評価の方法】
評価については、主に単元テストで行なっています。単元テストはB評価が獲得できる問題を事前に予告して行なっているため、どのレベルの生徒でも事前に勉強に取り組めば確実にB評価を取れるような内容にしてあります。その上で従来のテストのように教科書の範囲だけを知らせて行う問題も出題しており、その問題がある程度解ければA評価に近づくといった方法をとっています。
【良かった点】
第一に、生徒が自分の理解度に応じて進めているため、数学の得意な生徒はかなりハイペースで教科書を進め、高レベルな演習に取り組みやすくなり退屈しなくなりました。苦手な生徒はじっくりと教科書に向き合えるようになったことで焦って解答を写すだけになるといったことがなくなり、前向きに学習できるようになりました。
次に、生徒の理解度がより鮮明にわかるようになりました。苦手な生徒の中には教科書を正しく読めない生徒や、正負の数の計算でつまずいている生徒もいました。そういった生徒に声かけができるようになったことで、より生徒の実態把握ができたため教材研究の視点も広くなり、生徒に寄り添った工夫ができるようになりました。
【今後の課題】
現在は、1クラス30人未満なので目が届きやすいわけですが、40人規模になった場合にこの方法で対応できるのかといった不安はあります。また、1学年に複数の教科担当者がいて、評価の基準や教科書の進度を揃えないといけない場合も難しくなると予想しています。
≪私の日々の研鑽について≫
私は、若いころから外部セミナーに積極的に参加してきました。以前参加したセミナーを主催してくださった方々が、FacebookなどのSNSで次のセミナーや勉強会の告知をよくしてくださるため、なるべく参加するようにしています。現在は、離島に住んでいるため参加できる機会は限られますが、必ず最後の懇親会まで参加するようにしています。お酒は飲めないのですが、他の先生方の取組はとても参考になるためお話を聞くだけでも貴重な経験が得られます。最近は、オンラインセミナーも増えてきたためそちらにも可能な限り参加するようにしています。
また、校内で先進校視察の機会をいただける時は、なるべく積極的に利用するようにしています。セミナーや勉強会で知り合った先生方を中心に、実際の現場での取組を見せていただくことで大きな学びになっています。また、ICTを上手に活用している若手の先生に活用方法を教えてもらったりもしています。最近は生成AIの活用事例をよく尋ねています。校内で配付される教育情報誌にもよく目を通して、新しい視点がないか気をつけるようにもしています。
≪これからの教育について≫
近年の教育は、以前と比べて多様性が認められるようになってきたことに加え、ICT機器が普及したことで、生徒たちの学び方も多様化してきています。もはや、学校の中での学びだけで完結する時代ではないと思います。学校での学びが絶対であるといった姿勢ではなく、多様化する学び方からどの学び方が生徒の成長につながるのかを生徒と共に考えていくことが、これからの教育では重要性を増してくるのではないでしょうか。
これから先、様々な教育の形態がうまれ、教員にとってはその都度学び直す必要性がうまれることに負担を感じることもあると思います。しかし、目の前にいる生徒たちの未来のために、常にアンテナを高くはり、学び続けることが大切です。そして、我々が学び続ける背中を見せることが、生徒にとっても大切な学びになると思います。生徒と共に学びを楽しみ、生徒たちの未来のために頑張りましょう。