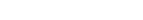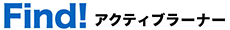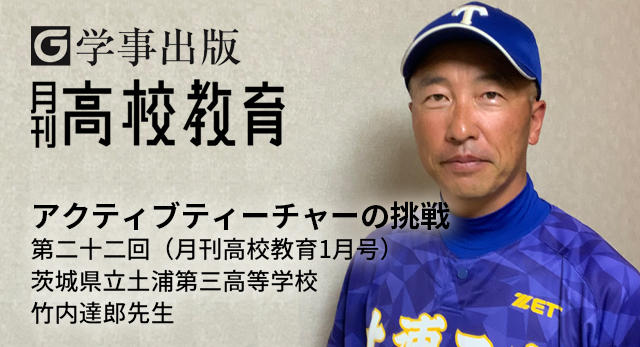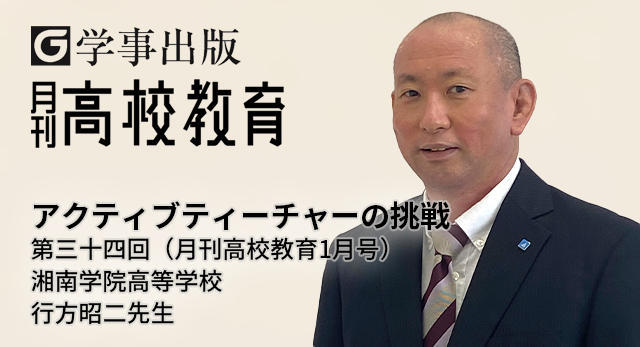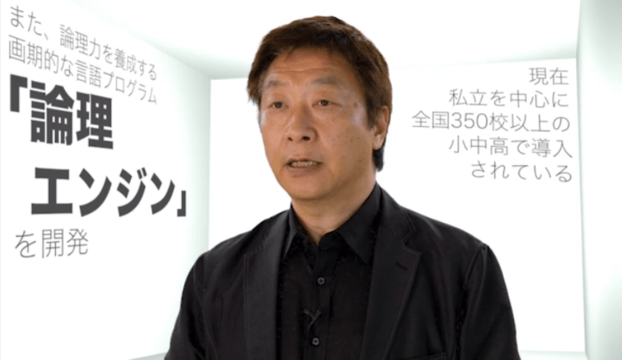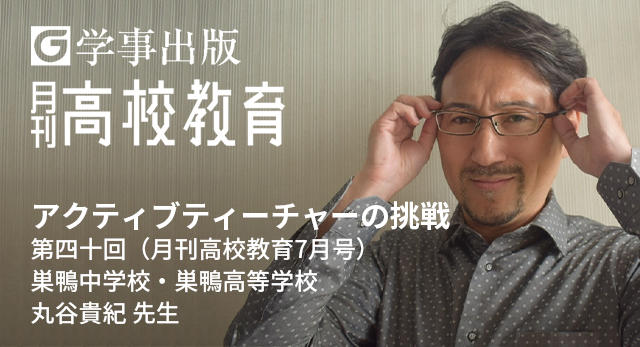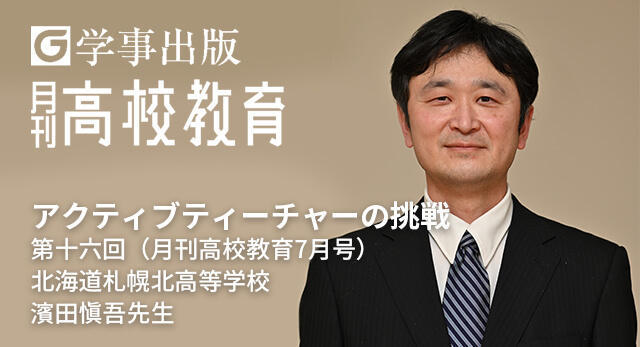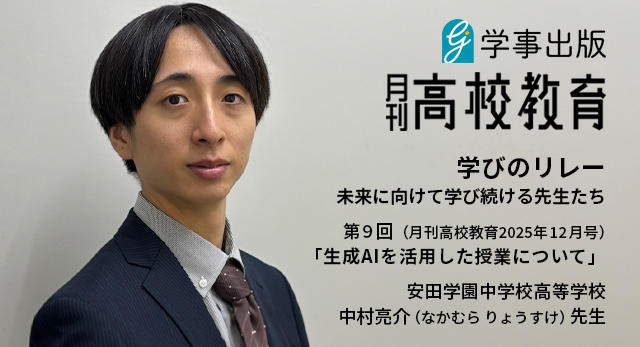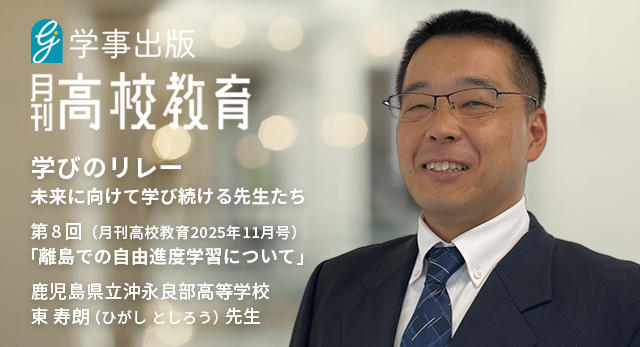学びのリレー 未来に向けて学び続ける先生たち 第6回(月刊高校教育2025年9月号)

学事出版『月刊高校教育』にてFind!アクティブラーナーの連載がスタート!
こちらでは冊子の記事をWEB版として公開しております。
学びのリレー 未来に向けて学び続ける先生たち 第6回(月刊高校教育2025年9月号)
芝浦工業大学附属中学高等学校
金森千春(かなもり ちはる)先生
「探究学習のカリキュラム設計」
≪芝浦工業大学附属中学高等学校について≫
本校は、1922年、旧国鉄で働く若者たちに中等教育の機会を提供したいという思いから、東京鐵道中学として開校しました。第二次大戦中には東京育英中学へと名前を変え、戦後の学制改革で東京育英高等学校に再編。その後、1953年に経営が芝浦学園へ移され、現在の芝浦工業大学附属高等学校へと移行していきました。1982年には板橋区坂下に移転。新校舎建設(板橋)に合わせて中学校を開設しました。2017年に豊洲移転、新校舎建設に合わせて校名を芝浦工業大学附属中学高等学校とし現在に至ります。
本校は一貫して「社会に貢献する人材」を「産業界の現場に」送り出すことを第一義に、教育を行ってきました。鐵中・育英時代は主に国鉄に、芝浦となってからは広く日本の産業界全体に有為な技術系人材を輩出してきたのです。そしてこれからも、本校は変わらぬ社会的使命を抱きながら教育内容を不断に改善し、名実共に優れた学校として成長し続ける学舎を築いてまいります。
本校の生徒は、ものづくりのマインドが根底に流れているのか、「とりあえずやってみる」「試行錯誤することを楽しむ」生徒が多いです。また、チャレンジ精神も旺盛で、新しいことに挑戦するフットワークの軽さも大きな特色だと感じます。それは生徒だけでなく、教職員や学校全体にそうした文化やマインドが共有されているからだと思います。学校全体が挑戦と創造を大切にする雰囲気に包まれていることが、生徒たちの成長に良い影響を与えていると感じています。
≪私のキャリアについて≫
私は、大学では理学部で数学を学び、新卒で教員になりました。高校3年生の時は、建築学科か数学科で迷い、どちらの学科も受験しましたが、数学科しか合格せず、進学を決めました。その際、担任の先生から「金森が数学科に行って教員になる道もいいんじゃないか」と言われたことも後押しになりました。数学科に進学し、その時から教員になる夢を持ちました。大学卒業後は、ご縁のあった学校で教員生活をスタートしました。本校では、勤続14年目になります。
2019年度には、東京理科大学大学院 理学研究科 科学教育専攻(修士課程)に入学しました。学部時代、ストレートで大学院進学も考えましたが、教授から「教育をやるなら現場を経験してから戻った方がよい」と助言を受け、一度教員になりました。その後、教授の退官が近づいたことや、当時科研費で進めていた「数学科における生徒自身による問題づくりと解説動画作成が単元理解に与える影響」の効果を実証したいと考え、大学院に進学しました。
仕事と大学院の両立は大変でしたが、現場経験があったからこそ、学びがより深まったと感じています。大学院2年目はコロナ禍で通学できない時期も多くありましたが、非常に貴重な学びの機会でした。今でも博士課程でさらに学びたい思いはありますが、仕事や家庭との両立への不安もあり、踏み出せずにいます。
≪探究カリキュラムの作り方≫
探究のカリキュラムをどのように作ろうかと考えたとき、まずは担当教員たちの「やりたいこと」をワークスペースであるMiroに書き出すことから始めました。IT (Information Technology)と GC(Global Communication)の2つのチームに分かれてコンセプトを検討・確定し、その過程で生徒に身につけてほしい姿勢やスキルを洗い出し、2年半の探究ITと探究GCでそれらを網羅できるようカリキュラムを設計しました。2020年度、1年間かけてじっくりカリキュラムを設計したのが良かったと思います。
探究に取り組む教員それぞれが自分の研究の流儀を持つなかで、共通の指針となる教科書が必要だと考え、本校では『学びの技』(玉川大学出版部)を探究の教科書として選定しました。本年度には第2版が出版され、内容もより探究的になりました。この教科書は、生徒だけでなく教員にとっても探究の基礎を学ぶ上で大いに役立っています。
また、探究学習に関する様々なネーミングについては。生徒からGoogleフォームで募集したり、担当者で書き出したり、色々な方法で、担当教員が楽しみながらつけています。
≪SHIBAURA探究について(4つの探究)≫
本校では、2021年度の中学入学生(共学1期生)からSHIBAURA探究をスタートさせました。SHIBAURA探究は、以下の4つの探究で構成されています。
○探究IT(中学1・2年、3年1学期)【隔週で週2時間(連続した2時間)】
探究IT(Information Technology)は、映画「アポロ13号」を観ることから始まります。限られた資源で課題を解決することの重要性を体感し、問題解決型の思考を育みます。本校の探究では、生徒も教員もワクワクできることを大切にしています。
○探究GC(中学1・2年、3年1学期)【隔週で週2時間(連続した2時間)】/strong>
探究GC(Global Communication)は、豊洲解剖図鑑の作成でスタートし、アメリカ修学旅行前の様々な生きづらさを抱える人の「オモイを知ってミライを創る対話」で締めくくります。他者理解と社会課題への意識を高めます。
○総合探究(中学3年2・3学期)【週2時間(連続した2時間)】
探究IT、探究GCで培った「探究に向かう態度」と「探究に必要なスキル」を生かして、「理工系の知識で社会課題を解決する」半期のプロジェクトに挑戦します。発表は2月の探究DAYで行います。発表を大切にするのは、High Tech HighのExhibitionの考え方に基づいています。
○工学探究(高校1・2年)【週1時間】
高校での「総合的な探究の時間」にあたる活動で、中学での探究の積み重ねをさらに発展させます。週1時間と限られた時間の中でも、自走力を身につけた生徒たちは、自らの力でプロジェクトを進め、2年間で1つのアイデアを実装することを目指します。「テクノロジーでセカイに新しい価値を創出する」「探究のクオリティを高め、プロトタイプを作成する」を目標とし、芝浦工業大学の7つの学問系統に基づいて緩やかなテーマ分けをしているのも特徴です。
◆書籍『PBLのカリキュラムデザイン』(芝浦工業大学附属中学高等学校 明治図書2024)について
この書籍は、第46回パナソニック教育財団特別研究指定校助成(2020〜2021年度)を受け、東北学院大学の稲垣先生の助言をいただいた中で、学校として探究してきた成果をまとめようと出版に至りました。
助成を受けながら試行錯誤してきた探究学習の経験を、多くの現場の先生方に届けたいという想いから、学校全体で原稿をまとめ上げ出版しました。この過程自体が、教員間の協働やカリキュラムの財産となっています。それまでは私も個人的な研究(科研費など)がメインでしたが、学校として研究に取り組み、研究助成は学校を変えていくエネルギーになることを経験しました。
◆本校のSHIBAURA探究について、より詳しく知りたい方は、以下のサイトをご覧ください。
https://sites.google.com/shibaurafzk.com/shibatan2024/
≪探究学習を進める上で大切なこと≫
市販の教材や、前任者が決めた教材や授業をただなぞるだけでは、探究を担当する先生の創造性も育たず、授業の楽しさも半減します。本校では、自分たちでカリキュラムや教材を作り、常にブラッシュアップを続ける探究学習を大切にしています。
そのために授業担当者には週1回の会議時間が授業コマとして確保され、授業内容の振り返りや改善、悩みの共有、議論を重ねながら進めています。週1回では足りないこともありますが、こうした時間の存在自体が「探究を大切にする学校」というメッセージになっていると感じます。
≪私の日々の学び・研鑽について≫
私は、現在、3つの学会に所属しています。大学時代から所属している日本数学教育学会、ICTと数学というテーマで研究した時に入った日本科学教育学会、そして2019年度に大学院に行った時に入った日本教育工学会の3つです。
これらの学会活動は、研究実績を積むためというより、純粋に学ぶことが好きで、最先端の知見や専門的な議論に触れたいという気持ちから参加しています。テーマごとに学会を選び、日本数学教育学会では数学教育、日本教育工学会ではインストラクショナルデザインや教育評価、日本科学教育学会ではそれ以外の幅広いテーマを学んでいます。
できる限り実践の発表(口頭発表、ポスター発表、論文)という形でまとめ上げ、同じ関心を持つ方々からご意見をいただくことで、大きな刺激を得ています。自分の実践と関連する先行研究を調べて新たなアイデアが浮かんだときの感動や、まとめ上げたときの達成感は、何ものにも代えがたいものです。
ここで、外部資金の調達についてお伝えします。これまで、個人としては科研費の奨励研究を、学校の研究代表としてはパナソニック教育財団の特別研究指定校助成や日産財団の理科教育助成など、さまざまな外部資金を獲得してきました。特に、SHIBAURA探究をともに牽引してきた技術科の岩田教諭も同様に外部資金を獲得し、私たちは「生徒の教育をより豊かにするために、外部資金を積極的に活用するべき」という姿勢で取り組んできました。
外部資金の活用は、単に教育活動の資金を増やすだけでなく、私たち教員が研究や実践に挑戦し続ける姿勢を若手教員に示すことにもつながります。それが、教員自身の「探究する姿勢」の重要性を学校全体に浸透させるきっかけにもなると考えています。
さらに、本校は芝浦工業大学の併設校であり、法人の研究推進課が中高の研究資金獲得を支援してくださるなど、大学と連携した取り組みも大きな力となっています。芝浦工業大学の教授や、芝浦工業大学柏中学高等学校の先生方と共同研究できることも、非常に恵まれた環境だと感じています。
≪皆さんへのメッセージ≫
私が2018年に購入したiPadの背面には、「Education should be more flexible.」と刻印しました。あれから7年。コロナ禍でICTが急速に普及し、探究学習や自由進度学習の広がりで教育は確かに柔軟になってきました。しかし、十分とはまだ言えないのではないでしょうか。授業の主人公は間違いなく子どもたちです。子どもたちが主体的に学び、興味を持てる授業を私たちは追及し設計し続ける必要があると感じています。
同時に、「学校に登校して学ぶ意味」「AIではなく私たちが授業をする意味」についても考え続けています。答えは簡単には出ませんが、生徒が学校に来て、私たちの授業を受ける価値のある学びを設計していきたいと思っています。