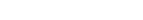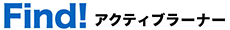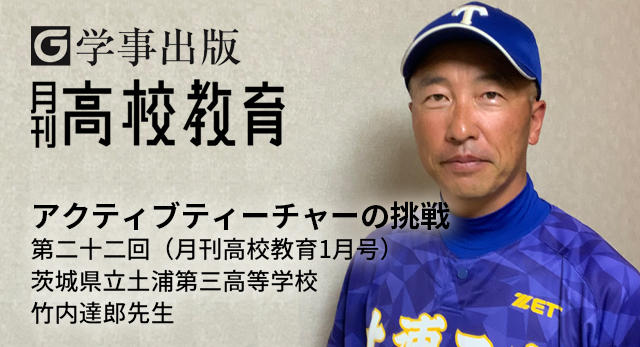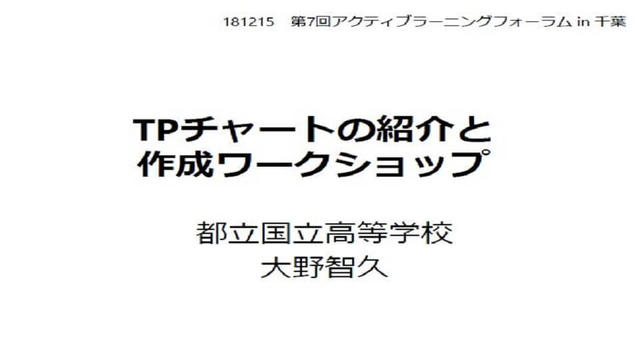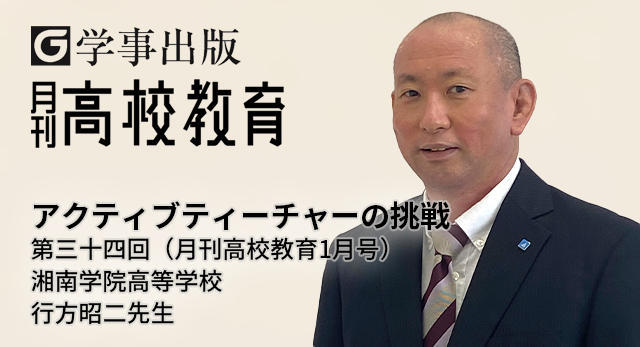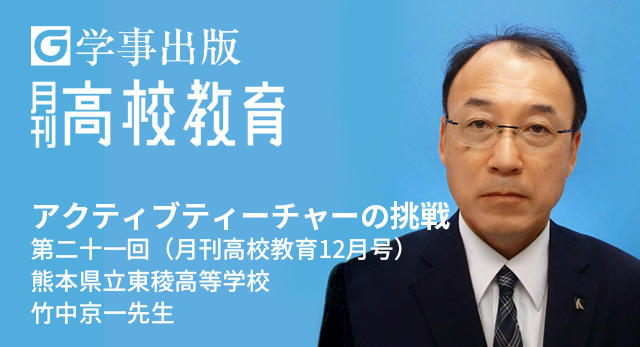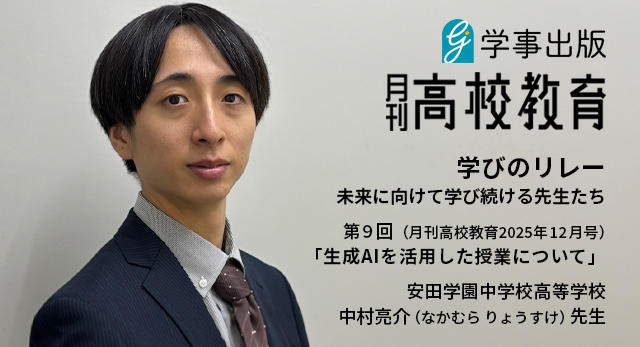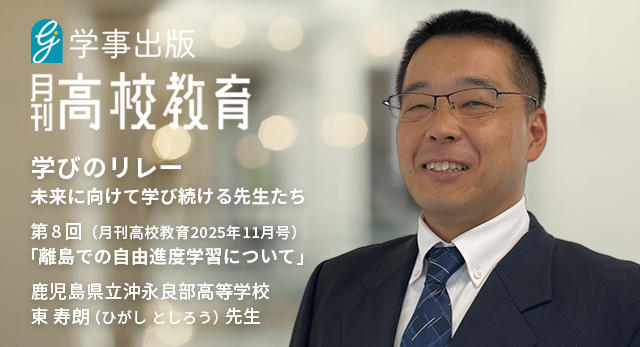学びのリレー 未来に向けて学び続ける先生たち 第2回(月刊高校教育2025年5月号)
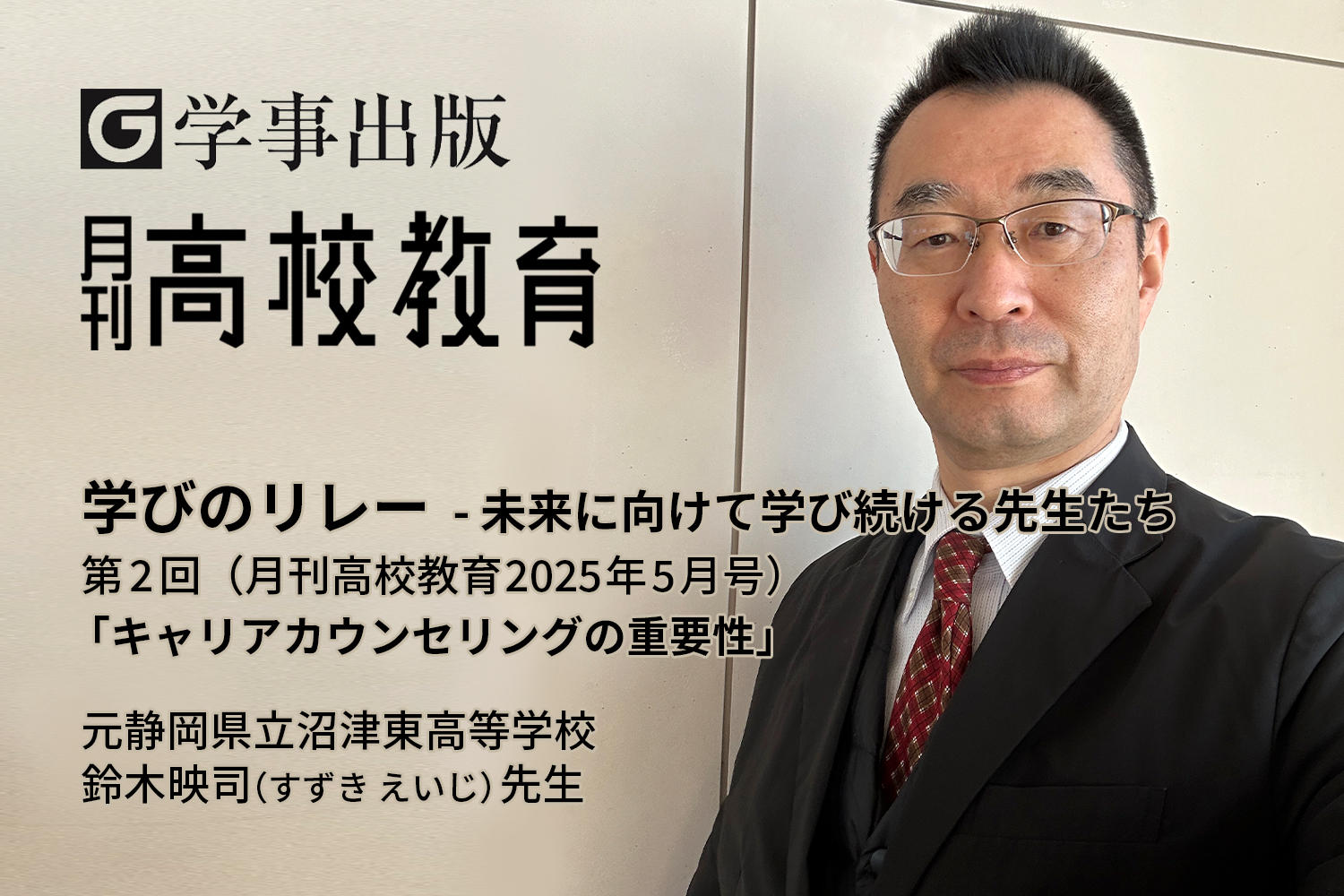
学事出版『月刊高校教育』にてFind!アクティブラーナーの連載がスタート!
こちらでは冊子の記事をWEB版として公開しております。
学びのリレー 未来に向けて学び続ける先生たち 第2回(月刊高校教育2025年5月号)
元静岡県立沼津東高等学校
鈴木映司(すずき えいじ)先生
「キャリアカウンセリングの重要性」
はじめに
昨今の変化が激しい社会の中で、キャリアを取り巻く環境は大きく変貌しています。この状況の中で高等学校における進路支援は、どうあるべきなのでしょうか。上級学校への進学や働くことだけでなく、どのように生きていくかというライフに関する関心も高まっています。進路指導とは、多様な価値観の中で自分の役割を見つけ出し、自分と自分の周囲と世界をより良い生き方、より良い未来に繋げるものだと考えています。
新学習指導要領が導入され、キャリア教育を柱とする「探究」が推進されていますが、キャリアカウンセリングの必要性も高まっています。「ガイダンスカウンセラー」と「キャリアカウンセラー」の有資格者としてここで提示しておきたいのは、キャリア教育には「ガイダンス」と「カウンセリング」の両輪が不可欠であるということです。
令和5年度まで学年主任として、キャリア教育を柱とした「総合的な探究の時間」(旧課程)を通じて進路ガイダンスを行ってきました。令和6年度には教育相談を担当し、全学年の生徒の希望者を対象にキャリアカウンセリングを実施しました。令和6年度のキャリアカウンセリングの取り組み状況と具体的な内容をここに報告し、公立学校普通科における導入の必要性と有効性について話題提供してみたいと思います。
静岡県立沼津東高等学校について
私は、長く静岡県の県立高校で勤務し、令和7年3月31日に静岡県立沼津東高等学校で定年退職を迎えました。ここでは、沼津東高等学校について紹介させていただきます。スクールミッションは、「静岡県東部地区の伝統的拠点校として、自治の精神を重んじ、生徒の主体的な学びを支援し、高い志の実現と社会の発展のために率先して行動する人の育成を目指します。」というものです。
内外各界で活躍する多くの著名人を輩出している伝統校であり、普通科7クラスと理数科1クラスからなる単位制です、特色としては自治会による生徒主体の学校生活、探究(「揺籃(ようらん)」)の取り組み、医療系人材の育成、海外研修、外郭団体の手厚い支援、広大な敷地などがあります。地域トップの生徒が集う学校で、生徒たちは、自治会活動・部活動と学習の両立に励んでいます。
キャリア教育について
キャリア教育とは、「自らの役割を見つけ出し、それを全うすることで、自分と、周囲と、世界を幸せにすること」を実現するための理論に基づく教育実践です。キャリア教育には「ガイダンス」と「カウンセリング」の両輪が不可欠です。日本における「キャリア教育の父」である仙崎武先生(文教大学名誉教授)は生前、「ガイダンスとカウンセリングがない学校は学校ではない」と語られていました。授業や部活動・クラス経営では全体指導と個別指導があるように、両方あって当然と考えています。
キャリア教育を柱とした進路ガイダンスの実施については、「『合格』ではなくその先で何をするかを目標に」、「予測できない未来、ひとりひとりの『その先』の物語を綴る作業」であると考えています。そこに向かって体験・経験・知識・技術を身に付けていきます。
キャリアカウンセリングの実践
カウンセリングとキャリアカウンセリングの違いについてまとめると、共通点は「対話を通じてクライエントをサポートする点」です。違いとしては、カウンセリングを司る心理カウンセラーは「心のケア」に重点を置き、キャリアカウンセリングを司るキャリアカウンセラーは「進路選択とキャリア形成支援」に焦点を当てています。現在、様々なキャリアに関する資格がありますが「日本キャリア教育学会キャリアカウンセラー」は学校でのキャリア教育にかかわる唯一の資格です。
私が令和6年度に教育相談担当として実施した、キャリアカウンセリングの実践についてお伝えします。実践の目的は、生き方に答えがない時代において、誰もが「キャリア」と「ライフ」の両立を考えなければならない時代に、必要な知識と技能を身に付けることです。仕事だけでなく、「ありのままの自分」を探り、「キャリア」を選び、「ライフ」を構築していく「マルチロールライフキャリア」の時代に必要な力を養います。
実践の概要としては、「相談室だより」を通じて、週一回昼休みに相談室で実施したところ、一学期中だけで12件の相談がありました。これは当初の予想を超える件数でした。依頼は生徒本人の他、ホームルーム担任教諭からの依頼も多かったです。進路の悩みからメンタルのダメージに繋がっている事例もあり、継続的に相談を受けるケースも出てきました。
実践の具体的方法、カウンセリングの手順と内容についてお伝えします。
(1)まずは健康状態を把握
(2)「カードソート法」によるマッチングアプローチ(新版OHBY・VRTカード)とWEB の活用ではジョブタグG検査を利用。
(3)価値観
(4)過去の自分との対話
(5)「ライフライン」
(6)現在と未来
(7)「ライフのタイプ」
(8)ツリー・オブ・ライフ
などのメニューを準備し、対話しながら「記録用ノート」にメモしていきました。
特に(2) 「カードソート法」はRIASECで知られるホラントの理論(The Holland Occupational Themes)に基づくもので個人の適性を判別するほか世の中にある仕事についての知識を広めることに使用しました。(4) 過去の自分との対話では、周りの大人からの期待に忖度することなく、生まれながらに各自持っている、自身の好みだけで無心に遊んでいた幼少期や歩んできた人生の転機を振り返ってもらいました。(5)「ライフライン」による振り返り、(6) 現在と未来の展望として、固定観念や周囲の期待にとらわれず多数の可能性をイメージする機会を設けました。そして、(7)「ライフのタイプ」では、どのような時間が持てれば楽しく働き生活することができるのかイメージさせました。
キャリアカウンセリングの成果と課題
キャリアカウンセリングに来る生徒には三つのタイプがあります。①学習の成果がなかなか順位として現れず、学校生活や学習に行き詰まって進路に関しても見通せなくなってしまった生徒。②学習成績は高いが何をしたら良いのかわからず目標が定められない生徒。そして、③校内外の活動に積極的に参加しているが活動の結果さまざまな迷いが生じてきた生徒です。高校生の進路は周りの期待や環境に左右されることが多いですが、自分の進路は自分で決めるという視点で、「主人公」として生きていける支援を目指しています。
課題としては、教諭の通常業務をしながら生徒とのカウンセリングの時間を持つには、どうしても時間的な制約があります。今後充実させたいのは、生徒にとって大切な毎日寄り添う存在であり、日々の安心・安全がベースとなっている担任教諭への研修だと考えています。生徒が主体的に活動するには、担任教諭がキャリアカウンセリングの知識と技術を持つことで、もっと多くの生徒の支援ができると思います。
日々の学び・研鑽について
課題が山積している今だからこそ、「理論と実践の往還」が不可欠だと考えています。D・クランボルツ(John D. Krumboltz)のプランド・ハップンスタンス(planned happenstance)理論をもとに、生徒が「探究」活動で身に付ける能力を分析しています。
大人も子どもも「探究」を続ける答えがない時代に、楽しく学び続けるためには好奇心と人との繋がりが大切だと思います。日本キャリア教育学会では探究推進委員を拝命し、地元ではLearning Design Communityという日本協同教育学会所属の教師の勉強会を結成しました。経験を持ち寄る自律した大人の学び(アンドラゴジー)の具現化を目指しています。学会参加によって、実践を学問的に分析したり、論文にまとめたり、国際発表をしたりする機会も得ることができました。
地理教員として、教科の知識の更新など、必要とする膨大な知識技能を得るために放送大学大学院選科生として(現在通算13年在籍)研鑽を積んでいます。
教育の未来について
答えがなく誰もが不安な時代に、その中でどのような未来を描くかというテーマについて考えています。ブラジルの教育学者パウロ・フレイレの『被抑圧者の教育学』からまもなく約60年、今もペダゴジーについて盛んに論じられています。今、教育に必要なものは一人一人の「自立と対話」であり、自分の殻を割って誰かのために何かをすることだと思います。他者に向けられたパフォーマンスによって初めて「アイデンティティー」は形成されます。「何もないと思えば何もない」「何かあると思えば何かある」、描いている夢に優劣はありません。
私は「生徒たちに、自分の人生を自分が主人公となって歩ませたい」という思いで、教員を続けています。自分が主人公の物語をつづる、物語をつくるのがキャリア教育です。一人一人の物語が変化すれば、未来も変わると考えています。
簡単な自己紹介
キャリア教育を柱に、授業改革、ICT などさまざまな取り組みを行ってきました。
日本キャリア教育学会キャリア・カウンセラー資格認定委員・一般社団法人日本スクールカウンセリング推進協議会認定ガイダンスカウンセラー。「日本学術会議小委員会委員(23期)」・ 文部科学省(国研)・厚生労働省などの協力者委員・ロイロノート認定TEACHER 等。IAEVG キャリア教育世界大会・協同教育学会(JASCE)台北大会発表。2015年Leaning Design Communityを結成。元静岡県立沼津東高等学校教諭、現在広尾学園中学校・高等学校非常勤講師。
・著書
『現場ですぐに使えるアクティブラーニング実践』
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784382057289
『アクティブ・ラーニング実践集 地理』
https://www.yamakawa.co.jp/product/59202
全国高等学校進路指導協議会でいくつかの教材を作成してきました。
https://www.jitsumu-kyouzai.com/highschool/show_product.php?pid=23
ライセンスアカデミー キャリア探究+plus進路選択 制作に関わりました。
https://licenseacademy.jp/industry/books
授業の面で、数々の取り組みをアカデミックにまとめた論文。
高校地理の授業における ICT 活用の事例
https://www.jstage.jst.go.jp/article/chirikagaku/77/3/77_171/_article/-char/ja/
・関連ホームページ
日本キャリア教育学会:https://jssce.jp/
日本協同教育学会(JASCE):https://www.jasce.jp/
静岡県立沼津東高校:https://numazuhigashi-h.school/
三菱みらい教育財団「揺籃(探究)」の紹介 (2024カテゴリー1 東日本準アワード受賞):https://www.mmfe.or.jp/partners/2890/
・前任校での実践
iTeachersTV 〜教育ICTの実践者たち〜 (9年前の動画)
https://youtu.be/BX2F9-OfAbA?si=w5JAJFnwXOLC5wp8