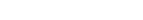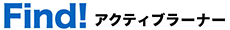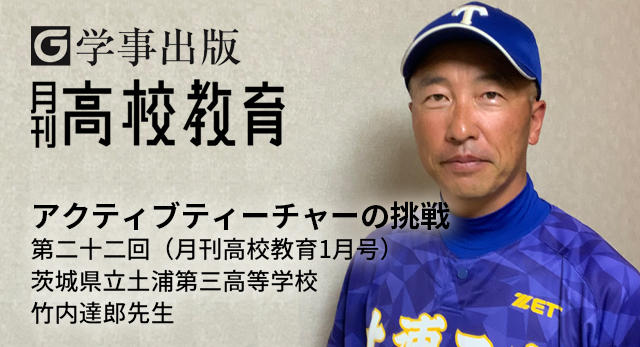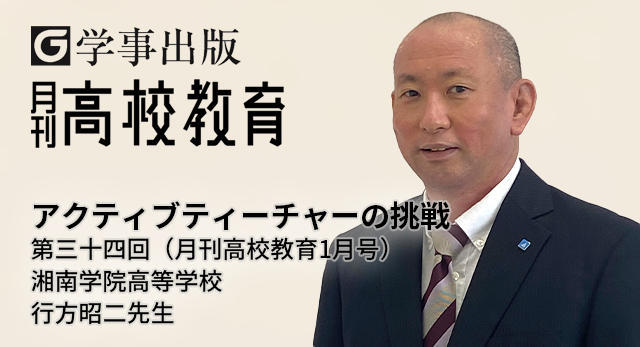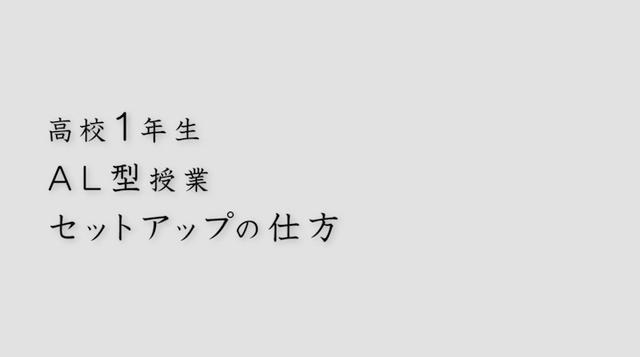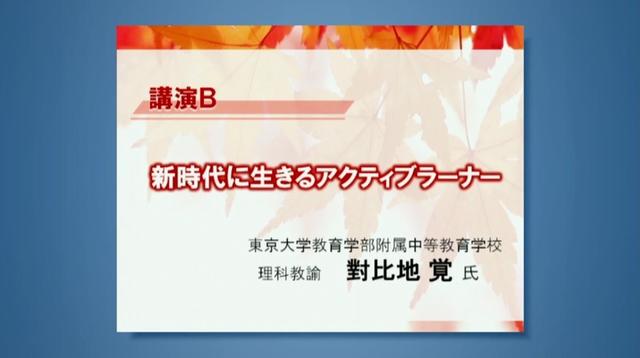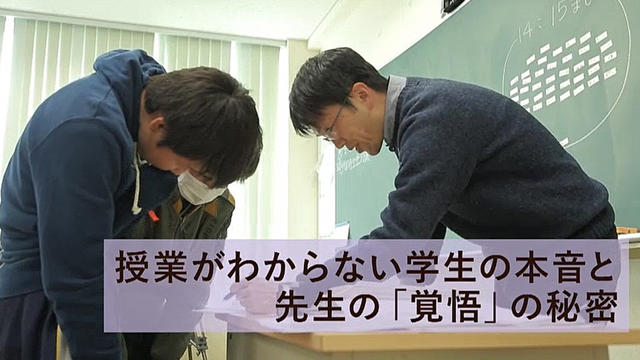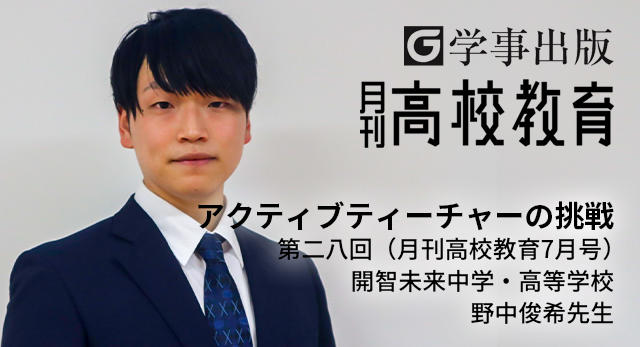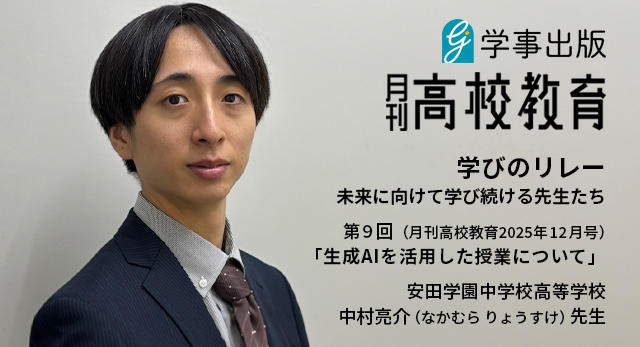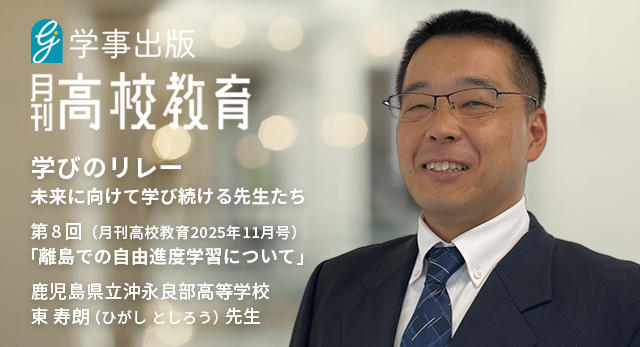学びのリレー 未来に向けて学び続ける先生たち 第9回(月刊高校教育2025年12月号)
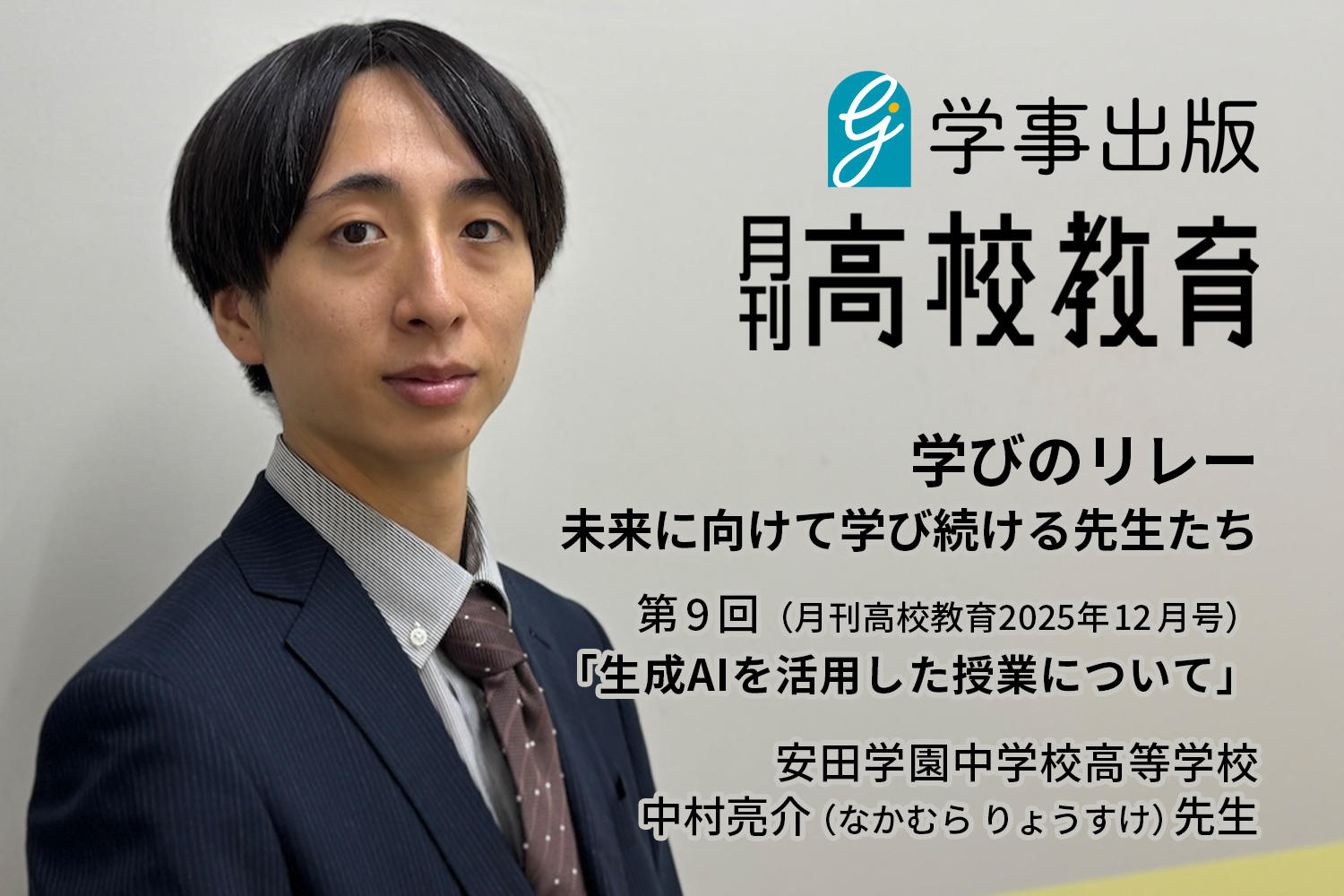
学事出版『月刊高校教育』にてFind!アクティブラーナーの連載がスタート!
こちらでは冊子の記事をWEB版として公開しております。
学びのリレー 未来に向けて学び続ける先生たち 第9回(月刊高校教育2025年12月号)
安田学園中学校高等学校
中村亮介(なかむら りょうすけ)先生
「生成AIを活用した授業について」
安田学園中学校高等学校について
本校は、東京都墨田区の両国に所在している私立学校です。1923年に安田善次郎翁の理念「実業界の有用な中堅人物の育成は、社会発展の基礎である」に基づき設立されました。常に社会に必要な人材を育成するという使命のもと、2012年に「自学創造」を教育目標に追加し、グローバル化する社会に適応するための学びを提供しています。
「自学創造」の実現をめざして掲げるのは、「学び力伸長システム」「進学力伸長システム」「キャリアデザイン」「探究」「グローバル教育・体験」「人間力教育」「クラブ・委員会活動」「体験行事」の8つのプログラムです。これらを効果的に実践することでグローバル人材を育成。将来、地球規模の問題を追究し創造的に解決するグローバルリーダーとして活躍することを願っています。
さまざまな経験を通じて、「仮説力」、「実行力」、「協創力」、「自己統制力」、「人間力」を身につけてほしいと、学業とともに人間形成の重要な場として、クラブ活動を奨励しています。勉強はもちろん、部活動や学校行事にも前向きな生徒が多く、何事にも活発に取り組む姿が見られます。例えば、6月に代々木体育館で実施している体育祭は、予行練習から当日の運営まで、生徒主体で行っており、たいへん盛り上がります。
≪私のキャリアについて≫
私が数学の教員を志望したのは、私自身が充実した学校生活を送れた経験があるからです。今度は私が、生徒たちにとって豊かな学校生活を送る一助になりたいと思っています。
大学卒業後、千葉県にある日本体育大学柏高等学校に着任しました。8年間の勤務中、2年目からは情報システム課に配属され、ICTに深く関わるようになりました。校内研修の講師を務める中で、私の在籍中にロイロノート認定校やGoogle for Education事例校に認定されるという成果を上げることができました。また、年1回のICTに関する公開授業や公開研修も企画・運営しました。進路指導部では、3年間のカリキュラム作成を主導しました。学習意欲の高い教員が多く、在籍最後の年には、放課後を活用した生成AIに関する勉強会も開催しました。
本年4月、母校である安田学園中学校高等学校に異動しました。教員歴は9年目となりますが、母校の生徒たちの未来のために、全力を尽くしたいと思います
≪生成AIを活用した数学の授業≫
生成AIを使い始めたのは、2024年度からになります。主に使っている生成AIツールは、Googleが提供している、「Gemini」になります。なぜ、「Gemini」を主に使っているかというと、理由としては、無料で使える幅が多いところです。例えば、Gem(特定の目的やタスクに合わせてGeminiの振る舞いをカスタマイズできる機能)や、Canvas(アイデアを形にするクリエイティブスペース)などが、無料で使えるからです。
私が日頃から活用しているのは、主に「問題作成」「授業の問いのシミュレーション」「数学活用授業案の作成」「授業の振り返り」です。これらはGeminiを活用することで、大幅な効率化と質の向上につながっています。活用頻度も多いため、Gemでの活用をしています。
「問題作成」においては、類題の作成や難易度の調整が容易になり、授業準備が効率的に行えるようになりました。「授業の問いのシミュレーション」では、生徒の思考を深める問いをGeminiに考えてもらい、さらに、それに対する生徒の反応のシミュレーションも行っています。これにより、実際の反応と全く同じではなくとも、「こんな反応があれば、こう質問してみよう」といった具体的な授業展開がイメージできるようになりました。
「数学活用授業案の作成」では、単元の最後に数学と実社会を結びつける授業を行う際、Geminiにアイデアを仰ぐことで、私一人では思いつかないような授業案が多数生まれました。これにより、これまで難しいと感じていた単元でも、実社会と関連付けた授業が実現できるようになりました。
「授業の振り返り」は、特に数学と実社会を絡めた授業の後によく活用しています。生徒の振り返りや私の狙いをGeminiに共有することで、客観的なフィードバックを得ています。これは、同僚の先生と話すように、多角的な視点から助言をもらえるため、今後の授業改善に大いに役立っています。
≪生成AI活用の特色あるアイデア≫
謎解き演習
生徒の学習意欲を高めるため、単調になりがちなテスト前の演習を「謎解き」形式にしました。演習問題の解答をパスワードの鍵とすることで、生徒は楽しみながら学習を進めていました。「今後もテスト前にやってほしい」という声が上がるほどの好評を得ました。
この謎解きアプリは生成AIを活用して作成しました。「どのようなアプリを作りたいか」を言語化できれば、生成AIがコードを書いてくれるため、ハードルが高いと思われがちなアプリ開発も、意外と簡単に実現できます。
○数学×芸術
数学と芸術のつながりを体験してもらうため、黄金比の単元で生成AIを活用した教科横断的な授業を実践しました。生徒にはプロンプトを提出してもらい、それを基に私が絵を生成します。一度生成された絵を見て、プロンプトを修正し、再度生成することで、「生成AIは一度で答えを教えてくれるツールではなく、対話を重ねることでより良いものが生まれる」ということを実感してもらいました。また、この授業の準備にあたり、芸術科の先生に絵に関するアドバイスをもらうことで、より質の高い授業を提供することができました。
○誤解答の作成
今年参加した外部の研修会でヒントを得て、「誤解答の作成」を生成AIに作らせるという手法を数学の授業に取り入れました。生成AIに意図的に間違った解答を出力させ、生徒たちにその間違いを見つけて正しく直してもらうという活動です。ただ問題を解かせるだけでなく、間違いを自ら発見し議論することで、生徒の理解がより一層深まると感じています。この方法は、どのような教科でも応用できると考えています。
≪生成AI活用授業の成果と課題≫
○成果
生成AIの活用により、これまで時間がかかるため実現が難しかったアイデアを簡単に形にできるようになりました。発想次第で、教育の幅を大きく広げられると感じています。校務も効率化されたことで、これまで十分に時間を割けなかった部分にも注力できるようになりました。また、ツールを導入する際に見失いがちな目的意識を、改めて見つめ直す機会が増えました。そして、生徒たちにとっては、数学が実社会のさまざまな場面で使われていることを実感する機会が増えたと思います。
○課題
生成AIの活用における課題として、「問題を解く」という授業スタイルだけでは、その真価を発揮しにくい点が挙げられます。単なる問題作成や解答確認に留まってしまう可能性があるからです。AIがさらに発展していく中で、数学を通して生徒に何を身につけさせるべきか、そして、そのためにどのような授業をデザインし、生成AIをいつ、どのように活用するのが最も効果的かを常に考える必要があると感じています。
≪校務での生成AIの活用≫
○生成AI推進チームの発足
今年度、本校に着任直後の5月、管理職の先生に提案して、生成AI推進チームを発足させました。メンバーを希望制で募集したところ、15名が集まってくれました。まずは校内の活用事例を増やすことを目標に、複数のグループに分かれて事例を検討し、その内容をチーム内で共有しています。現在は、それらの事例を全教職員に共有している段階です。
○校務で活用していること
校務では、メールの返信文書作成や、クラスで行うレクリエーションの企画、スライドの土台作成など、多岐にわたる場面で生成AIを活用しています。アイデア出しから修正までをサポートしてもらうことで、ほとんどの校務が効率化されました。生成AIに文書や企画を手伝ってもらうようになってから、出力された情報の正しさはもちろんのこと、元の文章の意図に沿っているかをより注意深く確認するようになりました。この習慣は、私自身の読解力や思考の質を向上させていると感じています。
○プロンプトゲートの活用について
本校では、昨年度から株式会社FCEの「プロンプゲート・アカデミック版」を導入しています。前任校の日本体育大学柏高等学校でも導入されていたものです。生成AIに不慣れな先生方には、まず「プロンプトゲート・アカデミック版」から複数のプロンプトを選んで活用してもらうことで、手軽に生成AIに慣れてもらう機会を作っています。また、すでに活用している先生方にも、プロンプトの書き方を参考にしてもらうために、積極的に見ることを勧めています。
≪私の日々の研鑽について≫
私は、現在、以下の資格を所持しています。
○Google for Education 認定トレーナー、Google for Education 認定コーチ
○ロイロ認定イノベーター、ロイロ授業デザイントレーナー、ロイロ認定ティーチャー
前任校である日本体育大学柏高等学校時代の先輩が、複数の資格を所持するとともに、外部からも常に学んで、広い視野を持っていることを尊敬していました。そして、私もそうなりたいと強く思いました。その思いが、資格取得に向けた学びの原動力となりました。
近年は、主にロイロノートやGoogle for Educationに関することで、私自身も登壇させていただく機会が増えています。
2025年度に登壇した研修会は以下の通りです。これから実施するものも含んでいます。
・ロイロノート公開勉強会@日大櫻丘2025ーICTツールと生成AIで授業をアップデートーNEXT GIGA時代の新しい学びー
・東京都市大学等々力中学校・高等学校「等々力ICTフェア 2025」
・飯能高校 ロイロノート研修会
・シンキングツール大研修会
・ミカサ商事主催Google for Education 活用セミナー「生成AIと共に創る数学の
授業 ~授業が変わる、思考が深まる数学教育~」
・GEG関東フェスタ 2025 Summer
・神奈川県立相模原城山高等学校 教職員研修(9月)
・日体大柏 公開研究授業+ICT活用研究会(9月)
・第7回東奥義塾ICT教育フォーラム2025(10月)
・ロイロノート×生成AI研修会 @安田学園中学校・高等学校(11月)
・GEG関東フェスタ 2025 Winter(12月)
2024年度以前に登壇した研修会の主なものは、以下の通りです。
・EDIX東京2023
・NICT教育推進校公開研究会•GIGA参観日in千葉県野田市
・流山市教育研究会数学部会
・答えのない教室inぐんま
○個人的な生成AIの活用法
個人的には、生成AIを相談役や壁打ちで活用しています。相談役や壁打ち用のGemを作成しているため、考えがまとまらないことや、他に考えるべきことがある時はGeminiと対話しています。対話してく中で、「なぜ」の質問をたくさん聞かれることや、私が考えてなかった視点に関しても話してくれます。文章として打つときもあれば、音声入力で対話することもあり、何か困ったことがあればすぐに活用しています。
≪未来の教育について≫
生成AIの進化に伴い、知識を教える分野では、その質がさらに向上していくと予想されます。これにより、教員は単に知識を伝えるだけでなく、生徒一人ひとりに寄り添い、学びをデザインするファシリテーターとしての役割がより重要になっていくでしょう。生成AIは、近い将来、私たちの頼もしい相棒になると考えています。だからこそ、教師がこの新しいツールとどのように向き合い、段階的に活用していくかが大切になります。今後は、これまで以上に生徒と向き合い、それぞれの成長をきめ細かく「見ていく」ことが必要になるのではないでしょうか。
皆さんも感じられているように、世の中は今後ますます急激に変化していくと思います。その中で、教員のあり方も変わっていくことでしょう。しかし、生徒たちの成長を願う気持ちは、いつの時代も変わらないと私は強く感じています。生成AIの進化に期待と不安の両方が高まる今だからこそ、皆さまと対話しながら、これからの教員のあり方について共に考え、成長していきたいと願っています。生徒たちが幸せな未来を歩めるよう、その一助となれるように、一緒に頑張っていきましょう。